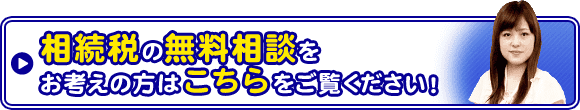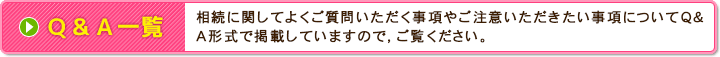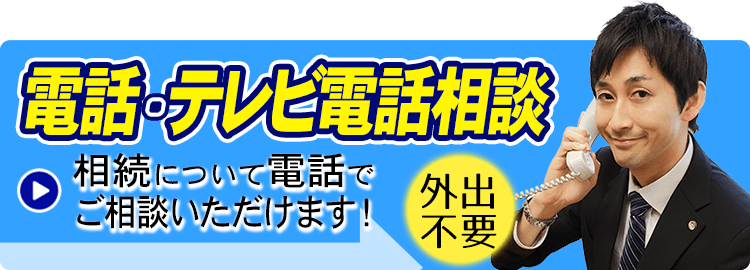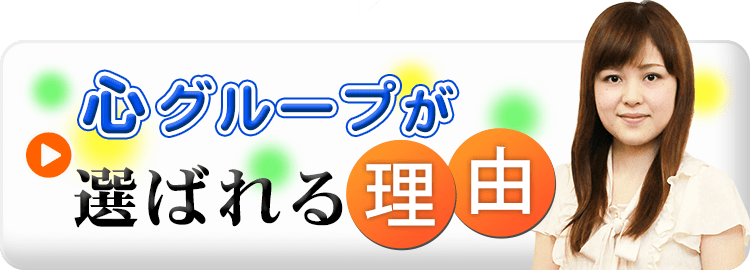みなし相続財産となる死亡保険金や死亡退職金について
相続人の中には、死亡保険金や死亡退職金を受け取ったり、亡くなる前数年間に贈与を受けたりした方も多いと思います。
民法上これらのお金は相続財産ではありません。
しかし「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる可能性があります。
もっとも、このみなし相続財産の中には非課税枠が設けられており、節税対策として活用できるものもあります。
そこで、今回の記事では「みなし相続財産」に焦点を当てて分かりやすく解説します。
1 民法上と税法上で違う「みなし相続財産」
「相続財産」の定義は、「民法」と「税法」とで違いがあります。
民法上では相続財産ではないものが、税法上では相続財産に含まれて相続税が課税されるケースがあるのです。
このように民法上は相続財産ではないが、税法上は相続財産に含めるものを「みなし相続財産」といいます。
まず、民法上と税法上の相続財産の違いを見ていき、その後、みなし相続財産とはどのような財産かを説明します。
⑴ 民法上の相続財産とは
「相続」とは、民法上次のような制度と考えられます。
民法896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
つまり、民法上の相続財産とは、「相続開始時に、被相続人が有していた財産上の一切の権利義務」ということになり、不動産・預貯金・有価証券・債務等といった財産のことを言います。
【民法上のもう一つの「みなし相続財産」】
「みなし相続財産」の理解を難しくしている原因の一つに、民法上「相続財産とみなし・・」という記述があることがあげられます。
民法の定義によると、次の財産を相続財産とみなす(みなし相続財産)ということになります。
「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額+特別受益 - 寄与分」
この場合は、この相続財産(みなし相続財産)の金額をもとに各相続人の相続分を決定することになります。
⑵ 相続税法上のみなし相続財産とは
税法上のみなし相続財産とは、被相続人が死亡時に有していた財産ではないが、被相続人の死亡によって発生する財産で相続財産と変わらないとみなされた財産のことをいいます。
例えば、死亡保険金や死亡退職金です。
死亡時に有していませんので民法上は相続財産ではありませんが、税法上は被相続人の死亡により発生する相続財産と変わりない財産とみなされて、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
相続税法上のみなし相続財産には、次のようなものがあります。(相続税法3条の「みなし相続財産」とは異なるものも含みますが、課税対象となる財産です。)
・生命保険の死亡保険金・損害保険金
・死亡後3年以内に支給額が確定した死亡退職金
・定期金
・相続前3年以内に被相続人から贈与された財産
(2024年1月1日以降の贈与財産は段階的に相続前7年までが課税対象になる)
・相続時精算課税により贈与された財産
・特別縁故者への分与財産
・信託受益権
・債務の免除
2 みなし相続財産の特徴
相続税法上のみなし相続財産には、次のような特徴があります。
⑴ みなし相続財産は相続人固有の財産
みなし相続財産は、被相続人から相続人へ相続により譲り渡すものではなく、相続人に直接支払われる(支払われた)相続人固有の財産です。
⑵ みなし相続財産は原則遺産分割協議の対象外
みなし相続財産は、相続人固有の財産のため、原則、遺産分割協議の対象となる相続財産に含まれません。
したがって、みなし相続財産は遺産分割協議書に記載する必要もありません。
⑶ みなし相続財産は相続放棄しても受け取れる
みなし相続財産は、相続人固有の財産で相続財産ではないため、仮に当該相続人が相続放棄を行っても、みなし相続財産は受け取ることができます。
3 みなし相続財産となる死亡保険金・死亡退職金について
ここでは、みなし相続財産の代表的なものである「死亡保険金」と「死亡退職金」について説明します。
⑴ 死亡保険金
生命保険の死亡保険金は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の組み合わせによって、みなし相続財産になる場合とならない場合があります。
次のケースでは、みなし相続財産とみなされて、相続時に相続税が課税されます。
・保険料負担者:被相続人
・被保険者:被相続人
・受取人:相続人・受遺者の場合
その他の組み合わせについては、以下の通り、「契約者 ≠ 被保険者、契約者 = 受取人」の場合は一時所得となり所得税が課税され、契約者 ・被保険者・受取人のすべてが異なる場合は贈与となり贈与税が課税されます。
| 契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
| 被相続人 | 被相続人 | 相続人、受遺者 | 相続税 (みなし相続財産) |
| 配偶者 | 被相続人 | 配偶者 | 所得税 (一時所得) |
| 配偶者 | 被相続人 | 子ども | 贈与税(贈与) |
なお、被相続人が保険料を100%負担していた場合は、死亡保険金全てがみなし相続財産となりますが、被相続人の負担が一部のみの場合は、被相続人が負担した部分だけがみなし相続財産になります。
例えば、被保険者と配偶者が保険料を負担していた場合は、次のようになります。
みなし相続財産 = 取得した死亡保険金 × 被相続人負担の保険料 ÷ 払込み済の保険料総額
なお、配偶者が負担した分については、次のように受取人によって、所得税あるいは贈与税が課税されることになります。
・受取人が「配偶者」の場合:一時所得として所得税
・受取人が「配偶者以外」の場合:贈与として贈与税
⑵ 死亡退職金
被相続人の死亡によって支払われた退職金は「死亡退職金」と呼ばれ、死亡後3年以内にその支給が確定した場合は、みなし相続財産となります。
一般的には、死亡退職金の受取人は会社の規程により決められています。
なお、死亡後3年以内に確定しなかった場合は、一時所得として所得税・住民税が課税されます。
4 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠
⑴ 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠とは
死亡保険金・死亡退職金といったみなし相続財産には、それぞれ非課税枠があります。
死亡保険金、または、死亡退職金から非課税枠が控除され、控除後の金額が相続税対象となります。
非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数え方は、相続税の基礎控除と同じ考え方です。
⑵ 非課税枠の計算
事例を挙げて、実際に非課税枠の計算をしてみましょう。
計算例:死亡保険金
被相続人:夫
相続人:妻、長男、長女
死亡保険金受取人ごとの死亡保険金額
・妻 1000万円
・長男 500万円
・長女 500万円
非課税枠=500万円×法定相続人の数=500×3=1,500万円
課税対象額=死亡保険金の合計-非課税枠=2,000-1,500=500万円
死亡保険金と死亡退職金の両方が払われる場合は、死亡保険金と死亡退職金のそれぞれから非課税枠が控除されます。
なお、相続放棄をした相続人はこの非課税枠が使えませんので、注意が必要です。
5 その他のみなし相続財産について
前項では、相続税法上のみなし相続財産の代表的なものである「死亡保険金」と「死亡退職金」について見てきました。
ここでは、その他のみなし相続財産について説明します。
⑴ 定期金
年金や保険金などが定期的に支払われる場合、その定期的に支払われるお金を「定期金」、その定期金を受け取る権利を「定期金の権利」と呼びます。
被相続人が個人年金等の掛け金を支払っていた場合はみなし相続財産となり、相続税の課税対象になります。
⑵ 相続前3年以内に被相続人から贈与された財産
被相続人から受ける生前贈与には、次の2種類の方法があります。
・暦年贈与
・相続時精算課税
暦年贈与には、贈与が行われた年の1月〜12月の贈与の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に、贈与税が課税されます。
しかし、「相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産」に該当する場合は、「みなし相続財産」となり、110万円の基礎控除以内の贈与についても基礎控除前の贈与額が相続財産に加算されます。
ただし、贈与が行われた年に贈与税を支払っていれば、相続税額から当該贈与税額を控除した税額を納税します。
2024年1月1日の贈与から加算期間が相続開始前3年から段階的に7年に延長
令和5年度の税制改正により、生前贈与の相続財産への加算期間が死亡前3年から7年へ変更となっています。
ただし、改正法施行後、いきなり加算期間が7年となるわけではありません。実際には、2024年1月1日の贈与から延長の対象となるため、この時期に贈与をしていた被相続人が2028年1月に亡くなると、はじめて加算期間は4年となり、加算期間が7年となるのは、2031年1月の相続からということになります。
⑶ 相続時精算課税により贈与された財産
贈与の一形態である「相続時精算課税」とは、原則、贈与時には贈与税が課税されず、贈与者の死亡時に、贈与者(被相続人)の相続財産に含めて相続税が課税される制度です。
そのため、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産も、みなし相続財産として相続財産に加えます。
⑷ 特別縁故者への分与財産
例えば、身体の不自由な被相続人の世話をしていた知人などは、家庭裁判所への請求により「特別縁故者」と認められれば、被相続人の遺産の分与が受けられます。
特別縁故者として遺産の分与を受けた場合は「遺贈」の扱いとなり、みなし相続財産として相続税が課税されます。
ただ、特別縁故者は被相続人の配偶者・一親等の血族に該当せず、相続税の2割加算の対象になりますので、注意が必要です。
⑸ 信託受益権
「信託」とは、財産を信託銀行等に預けて管理・運用を任せることをいいます。
被相続人が信託して、その利益を相続人が受け取る場合は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
⑹ 債務の免除
遺言によって、被相続人に負っていた債務が無償で免除された場合、あるいは、著しく低い価格で債務が免除された場合は、その免除された債務に相当する金額がみなし相続財産として相続税の課税対象になります。
例えば、被相続人に対して1,000万円の債務を負っていたが、遺言により無償で免除された場合、あるいは、10万円でその債務が免除された場合は、免除された額1,000万円、あるいは、990万円がみなし相続財産となります。
⑺ 弔慰金
被相続人の死亡によって受ける弔慰金は、通常、相続税の対象とはならず非課税です。
しかし、弔慰金は、金額がいくら大きくても非課税というわけではなく、下記の場合は、死亡退職金として相続税の対象になります。
業務上の死亡の場合
弔慰金が、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額を超える場合、この金額を超える部分は死亡退職金として相続税の課税対象となります。
業務上の死亡でない場合
弔慰金が、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額を超える場合、この金額を超える部分は死亡退職金として相続税の課税対象となります。
6 みなし相続財産についての注意点
最後に、みなし相続財産が含まれている場合の注意点について見ていきます。
⑴ 相続放棄をしてもみなし相続財産は相続税の課税対象
みなし相続財産は相続税の課税対象ですので、たとえ相続放棄を行っても、相続税を納めないといけません。
⑵ 原則、遺留分の算定対象外
みなし相続財産は相続人固有の財産ですので、原則、遺留分侵害額請求の対象外です。
ただし、相続人間で著しい不公平が生じた場合は、みなし相続財産が特別受益に準じて持戻しの対象に該当し、遺留分の対象なる可能性があります。
なお、みなし相続財産(生命保険金)が相続財産に含まれるかについて平成16年10月29日に最高裁判所で次のような判決がでています。
この判例は、相続人の一人が受取っている生命保険金が特別受益に該当するかどうかを争った事案です。
最高裁のこの判例でも、これまでの判例の通り「生命保険金は相続財産に属さない」という原則を確認しています。
一方で、注目すべきは、生命保険金を受取った相続人とその他の相続人の間で、到底是認することが出来ないほどに著しい不公平が生じた場合は、当該保険金が特別受益に準じて持戻しの対象に該当すると判示している点です。
結論として、生命保険金は、原則、相続財産に含めないが、個別案件の事情を総合的に判断して、場合によっては相続財産に含まれることもある、ということです。
参考リンク:裁判所・最高裁判所判例集
7 まとめ
今回は、「みなし相続財産」について見てきました。
中でも「生命保険金」は多くの方が相続税の課税対象になっており、生命保険金以外でも、在職中に亡くなった場合は「死亡退職金」、生前譲与を行っている場合は「被相続人死亡前の一定期間に贈与された財産」が課税対象になるかもしれません。
みなし相続財産は、名前の通り「相続財産とみなす」ことから相続財産に入れ忘れやすい財産であり、また、死亡保険金や死亡退職金といった非課税枠があるものもありますので、正しく理解した上で相続手続きを行わないといけません。
また、通常は、みなし相続財産は遺産分割協議に含まれず、遺留分の対象外ですが、相続人間で著しい不公平が生じる場合は、特別受益に準じて持戻しの対象となる場合がありますので、注意が必要です。
一方で、みなし相続財産は節税対策にも活用できますので、ご自分の相続対策の一環と位置づけて、生前より検討されると良いでしょう。
生前贈与で「現金手渡し」は有効か 孫に財産を承継させたいときの家族信託の使い方